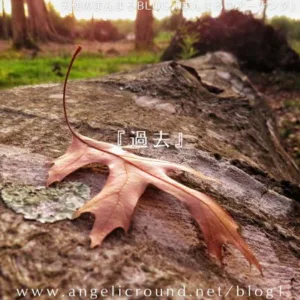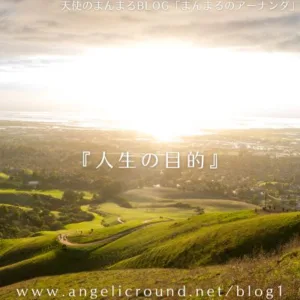今日は、本に関するお話です。
この間読了したのが、
アントニオ・G・イトゥルベ著『アウシュヴィッツの図書係』です。
Twitterで出版社などの読書に関する呟きを見ては、
次に読む本の参考にしているのですが、
この本もまた、ずっと気になっていたものでした。
これは実話が元になっています。
本はとても危険だ。ものを考えることを促すからだ
アントニオ・G・イトゥルベ著『アウシュヴィッツの図書係』
途中に出てくる文です。
ナチスはそう考えたのですね。
だから、
収容された人たちには本を与えることをしなかった。
本も迫害したのです。
でも、密かに持ち込まれた僅かな本を、
ある少女が、秘密の図書係となって手渡していく。
収容所の様子など、
悲惨なんて言葉じゃ表せないものだし、
こんなこと、
もう二度とあってはならないと思っています。
そしてまた、私はこの本から、
「本」について教わったように感じているのです。
先ほど引用した文をもう一度載せますね。
本はとても危険だ。ものを考えることを促すからだ
アントニオ・G・イトゥルベ著『アウシュヴィッツの図書係』
本は、ものを『考える』だけではなく、
ものを『感じる』こともまた促しているものだと思うのです。
少し前に、
Twitterで見かけた気になる呟きがありました。
投稿者の方は、
著名な人たちに会うことが多く、
そこで有意義なお話を聞く機会があるため、
本なんて必要ないと言っていました。
まぁ、
若い人の粋がった言葉かもしれないので、
そのままそっくり受け取るのもどうかと思いますが、
「本」というのが、
どういうものなのかを考えるヒントになったので、
興味深い呟きだなと思いました。
「聞く」と「読む」。
確かに、手に入れる内容は同じかもしれません。
でも、
受け身で手にしていくものと、
能動的に手にしていくものは、
異なるのではないかと思うのです。
分かりやすいのは、
学校で授業を聞いていることかな。
先生の話を聞いているだけで、
何でも身につく器用な方もいるかもしれません。
私は不器用なので、
主体的な方法で受け取っていくことしか出来ないから、
それを書いたり(何度も)、まとめたり、
口に出したりなどしながら、
なんとか身に着けていきます。
今はさらに覚えが悪くなっているから、
途中でイヤになってくるかもしれませんけど(笑)
それでも、自分から働きかけたものは、
どこかで自分の血肉となっているのだと思います。
本は、そういうものなのではないかと思うのです。
誰かに読んでもらうということも素敵なものですが、
自分で読むことで、
何かを感じ、想像をし、考えていく体験は、
最高だと思っているのです。
与えられる物ではなく、自分から手にしていくもの。
泥臭いのでしょうけれど、
私は主体的に生きることを大事にしているので、
やはり、受け身は別のものだと思うのです。
受け身の場合は、
与えられなかったら、
手にしない(出来ない)のですものね。
そんなのまっぴらごめんです。
自分の頭で考えて、
自分の心で感じていきたい。
こうやってものを考えたりするから、
支配しようと望む者たちには、
本が邪魔で仕方がないのかもしれませんね。
今、自由に本が読めること。
それがとても大事なことだとあらためて思っています。
この本の後に、
クリスティーナ・ダルチャー著『声の物語』を読んだので、
余計に、ものを考えたりすること、
それが取り上げられることなどについて、
さらに考えさせられています。
いろんなこと考えたり、感じることが出来る読書体験は、
捨てたくないし、捨てられたくない大事なものだと、
あらためて思う機会となった本たちでした。
今日もまたお読みくださいまして、
ありがとうございます。
たくさんの愛と感謝を。
七夕、いろんな願いが叶っていきますように。
追記:あなたのお勧めの本があったら教えてくださいね。
(実用書よりも物語が好きです)
天使のまんまるでは、
リーディングやアニマルコミュニケーション、
天然石グッズなどの癒しの道具販売など行っております。