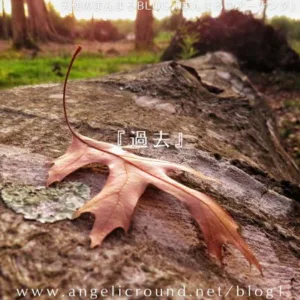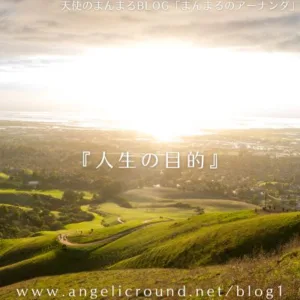さて本日は、この前、お坊さんから聞いたお話です。
少し落ち着いてきたので、
デンデの供養にと、先日お寺に行きました。
うちの子たちがお世話になっているお寺は、
毎日お昼の勤行があって誰でも参加出来るので、
都合がいい時にお邪魔しています。
カリンの時には七日毎に出かけていましたが、
デンデの場合は、父の入院や旅立ちと重なっていて、
疎かになってしまっていたので、
やっと行けた〜♪って感じでした。
お経が終わると、
お坊さんが少しお話をしてくれるのですが、
その際に次のようなことを仰っていました。
「日々、暖かな日が続いてきていますが、
気温差もある時ですので、
皆様、体調など、
どうぞお気を付けてお過ごしください。
皆さんが健康ではないと、
こうして供養もできませんので、
まずは皆さんが健康に過ごすことが第一です。
どうぞ、ご自身を大切に健康にお過ごしください。
それからのご供養です。」
んだんだ(笑)
頷いてました😁
人も動物も有名ではない場合、
悲しんだり供養したりする人は、
それほど多くないのではないかと思います。
それこそ『家族』だけが、
覚えていることが多いのではないでしょうか。
そして、覚えている方が、
その後の供養を続けたりしていることもあるでしょう。
供養というのは宗教的なものなので、
しないこともありだし、
信仰の違いもあるから、
こうしなくてはいけないということではありません。
私自身は、仏教の教えは好きですが、
信仰しているというとちょっと違うかな。
動物家族のことを思う1つの行為という感じです。
ただ思っていたのです。
どういう形であれ、
旅立っていった人でも動物でも、
供養していくには、
供養する側の人間が健やかでいなければできないと。
健康でいなければ供養をすることは出来ないと。
だから、お坊さんの言葉に深く頷いていました。
「私も連れてって」
「生きる望みなんて何もない」
「迎えに来て」
という気持ちは、
死別の苦しみの中で生まれていくものだと思います。
悲しみの過程の中では、
体験していくこともある感情です。
だけど、そこに留まり続けていたら、
旅立っていった方の供養はできません。
代わりに誰かがやってくれるかもしれないけれど、
誰もいないかもしれない。
立ち上がれないほどの悲しみに飲み込まれていたとしても、
供養という行事があるのは、
「供養してほしい」
という亡き方からの要望ではなくて、
「供養するということで、何かができる。
動いていくことで、
悲しみから立ち上がり、
日々を暮らして(生きて)ほしい」
という亡き方の想いだとしたら、
などとも思ったりしています。
まずは今を生きている自分から。
それから出来ることを。
やれることを。
そうやって生きていきませんか。
生きていきましょう。
死別の苦しみを抱えている方が、
少しでも健康で毎日を暮らせますようにと祈っています。
今日もまたお読みくださいましてありがとうございます。
たくさんの愛と感謝を。
追記:いろいろとご心配くださっているのではないかと思いますが、
強がりでも何でもなく、
いたって平静に過ごしています。
これもあなたのおかげです。
それに、ムテンが張り切ってお散歩に行くので、
とにかくお腹が空いて、
ちょっと体重が増量しちゃいました〜、てへ😂😅
天使のまんまるでは、
リーディングやアニマルコミュニケーション、
天然石グッズなどの癒しの道具販売など行っております。